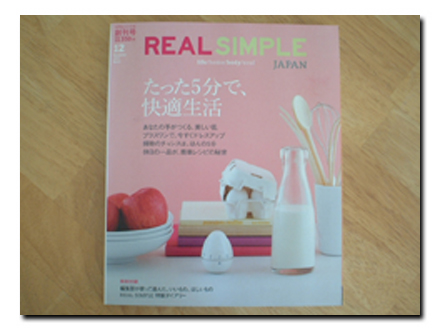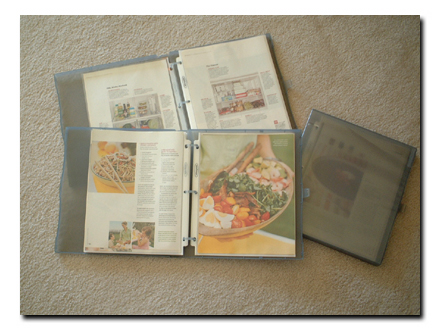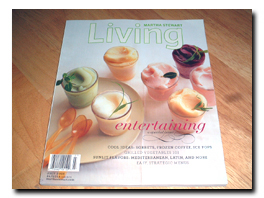'*★ シュシュ作りました♪ ★*'
妹が本を出したのですが、その中に基本の作り方が書いてあったので、作ってみました。
髪をとめるときはクリップタイプのものを使っていたのですが、自分に合うものがなかなか見つからないのと、割とすぐ壊れてしまうので困ってました。
シュシュだとこわれることもなくって便利。もっと作ろうと思います♪
'*★ オリンピック落選 ★*'
2016年のオリンピック候補地。
「シカゴに決まったら行けるかな」なんて頭の中で考えていたら、金曜日の朝、「シカゴ落選」のニュースを聞き、がっかり。
でも東京になるかも、と頭の中で、「行くとしたら計画をたてなくちゃ」なんて考えていたら、金曜日の夕方に落選のニュース。ショック。
頭の中が忙しかったです(笑)
ところで以前、
祖国へ、熱き心を-東京にオリンピックを呼んだ男 (講談社文庫) (高杉良著)を読んだのですが、すごくおもしろかったです。 (高杉良著)を読んだのですが、すごくおもしろかったです。
戦後、国がスポーツ選手にお金を避けない頃、自ら選手をロサンジェルスでサポートし、1964年の東京オリンピックの招致を実現に向けて動いた人の話です。オリンピックを招致するにもいろいろあるんですね。
'*★ 小手鞠るい 「エンキョリレンアイ」 ★*'
発売から5ヶ月で売り上げ10万部を突破した 小手鞠るいさんの
エンキョリレンアイ を読みました。
を読みました。
97年に知り合いの作家の川滝かおりさんのことを書いたことがあります。その後、彼女の作品である「国際恋愛図鑑」の感想を書いたことがあります。
この「川滝かおり」さんが「小手鞠るい」さんです。 2005年、第十二回島清(しませ)恋愛文学賞を受賞されています。受賞作は、
欲しいのは、あなただけ (新潮社)。
(新潮社)。
私は、恋愛小説は滅多に読みません。もともとそんなに好きじゃないっていうこともあるんだけど、結末が悲しいことが多いのと、自分に合わなかったときの「時間を返せ」的な脱力感が嫌だから。
でも、思い立って読み始めたこの小説。一気に読んでしまいました。静かに流れるんだけど、テンポがよく、入り込んでいく感じ。
主人公の花音(かのん)が本屋さんでの最後のアルバイトの日に、客として来た海晴と知り合いますが、留学中の海晴はアメリカに戻り、2人のやりとりはメールを通して始まります。
とても丁寧につくられた作品だと思います。
まず、背景の事実関係の正確だと思いました。
物語は1993年のことですが、私は94年にあの地区へ留学しています。当時、私も向こうでメールをやりたいと思い、日本からノートブックを持っていきました。
ウィンドウズ95の出る前で、設定が難しくて、なかなか日本語のメールを送る環境にはできませんでした。インターネットは走りで、検索もできない時代。知っていそうな人を探しては聞き、四苦八苦して、やっとなんとか始めたメール。海晴の、最初の設定に戸惑ったというメールに、「そうそうそうなんだよ」と苦笑しました。
また、筋とは直接関係ないんだけど、当時は、メールの行き違いのトラブルもたくさんあって、送られたメールが文字化けしてた、メールを受け取れなかった、ルームメートやクラスメートにパスワードを盗まれてひどい目にあった、なんていうのも日常茶飯事でした。
留学する前の年に「高校教師」を見て毎回、泣けるストーリーだった記憶があって、その辺もなつかしかったです。
ストーリーに出てくるCIA(The Culinary Institute of America)という料理学校は、私も行ったことがあります。書いてある通り、とても厳しいらしく、普通の大学のキャンパスと違って、休憩している人たちは、本当に疲れをとっている印象を受けたのを覚えています。
世界でも1位2位を争う料理学校ですが、"CIA"という名前のため、知らない人はFBIやCIAと混同してしまい、私は最初は警察官を育成するようなとこだと思ってました(笑)。カリフォルニアのナパにもありますね。
登場する町は、だいたい知っている場所で、なだらかなキャッツキル山脈と自然がとけ込んだ美しいところです。海晴のレポートの通り、花音の経験した通り、です。物語用に作られたものではありません。
2人の間が盛り上がって、危機がくるだろうということは読んでて想像できます。それでも何も起こらないこともあるし、どんでん返しが起こることもある。
「この感動した気持ちを裏切る展開にはならないで」と祈りながら読み進みました。どんな結末になっても、登場人物の誰かひとりは、私を裏切らないで欲しい、と。
文章のところどころで感じる「何かくる」感じ。やがて訪れるであろう終わりはどこでどんな形でくるのか。それとも、もしかしたらこの感覚は錯覚か。
この作品は「名作」と言えると思いました。
いつまでも心に残って、余韻を味わうことができます。「言葉」と「余韻」を感じられる本だと思います。同時に、あとでじっくり考えてもボロがでない、というか、「気持ち」の矛盾がない作品だと思いました。
女性だけでなく、男性も楽しめる作品だと思います。映画化されたら、とても美しい画像になると思うんだけど。ニューヨークのアップステート(マンハッタンではないとこ)は本当にきれいなところです。
小手鞠さん(とここでは呼びます)の他の作品も読んでみようと思いました。
'*★ 雑誌 Real Simple Japan 創刊 ★*'
昨日、サンノゼの紀伊国屋で偶然見つけた日本版の「リアルシンプル(Real Simple Japan)」創刊号。この本、いいですよー。私は、3年くらい前にこっちでオリジナルの英語版を見つけて、その後2年くらいずっと買ってました。ちょっとマンネリ化してきて今年は買ってないんだけど、そのうち、ここでも紹介しようと思っていたところでした。
日本版はまだ詳しく読んでいませんが、この本は、life/home/body/soulがサブテーマで、生活のコツみたいなことがすべてにわたって書いてあるはず。
たとえばお料理では、レシピが載っているだけでなく、1日めのレシピ、2日めのレシピ、そして3日めは残りものでこんな風に作ろう、というようなことが具体的に書いてあって、そのメニューを実行するための買うものリストが細かく載せてあったりします。1ヶ月分のメニューとリストを載せている月もあり、とても便利でした。
また、たとえば2月号では「そろそろ夏の計画をたてよう」とか、12月号は「午前中に郵便局に行くこと」など、具体的に何をすればいいかが書いてあり便利でした。
新鮮な野菜の見分け方や、各野菜はどれくらい保存できるか、冷蔵庫の整理方法などの他、忙しいときの雑誌の切り抜き方法の提案、アイロンの効果的なかけ方、いろんなよごれの落とし方など、すべてに具体的に細かく書いてあります。
日常の生活面では、医療の基礎知識とか、各サービス業会の電話応対カスタマーサービスがどれくらい待たせるかを調べたり、クレジットカードのメリットデメリットが詳細に載っていたり、インターネットの便利な使い方、喜ばれるプレゼント、予定のたて方、時間の使い方など、スポンサーにこだわらない大胆な内容を載せてあります。
他にも、体型に合わせた洋服の組み合わせや、収納方法の提案、子供との対話、不幸にあった人には言ってはいけないタブー、化粧品の比較など、年齢を問わず幅広い層に向けてあるような気がします。(でも、20代後半以上に向けてるのかな。)
気に入った記事は、捨てる前にほとんどスクラップしています。近いうちにまた買おうと思ってたんだけど、日本語版と順番に買おうかな。比較もできるし、広告も読めるし。
ほんとに、久しぶりにおすすめできる雑誌です。Webサイトはこちら。創刊号には、11月から使える2006年のダイアリー(大きめの手帳)がついてました。350円。
'*★ 雑誌「Living」 ★*'
アメリカのカリスマ主婦、マーサ・スチュワートの出している月刊誌。
私は雑誌はお風呂の中とか寝ながら読めるくらいの軽いのが好きで、分厚いのは買わないんだけど、久しぶりに見たら、とても薄くなっていたので買ってみた。やっぱり株インサイダー取引の禁固刑が影響して、広告が減ったのでしょうか。
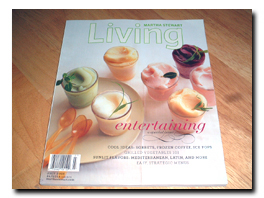
日本のカリスマ主婦、栗原はるみさんが出してる季刊誌が似ていると評判になったこの本。確かに載っていることは似てるんだけど、盗作という感じじゃなくて、2人とも同じ主婦でアイディアが豊富、という感じ。
「すてきレシピ」はどのページもすべて栗原はるみのアイディアで構成されている(らしい)のに対して、Livingは、記事を提供するエディターがいて、ひとつひとつの記事にはマーサは出てこないものもある。
でも、これほどまでにマーサが出てこなかったっけ?7月号では出てくるのは最初のパイを焼く記事だけで、あとはぜんぜん。それに以前あったマーサの1ヶ月の予定表のついたカレンダーもなくなってるし。手抜きになってしまった感じが否めないなぁ。
'*★ つれづれノート13(銀色夏生著) ★*'
銀色夏生の「つれづれノート」は、彼女が毎日のことを綴った日記で、1年に1冊づつ出して最新が13巻。2度の結婚と2度の離婚を経て、それぞれの相手の子供を連れて出身地の宮崎に帰り、自分の家をたてたところ。この13巻は、2003年4月から2004年3月までの日記です。
この本は久しぶりに読んだので、なんとなく他も読み返しているうちに5巻から12巻まで読み直してしまった。今まで読んでいなかった7,8巻も新たに買い足したりして。文庫になっていると、いつでもどこでも気楽に読めるのがいい。日記だから、半ページ読んでやめるとかも簡単にできるので、夕飯作ってる合間に台所で2,3ページ読んだり、買い物でレジに並んでるときや、歯医者で待ってるときなんかもちょこちょこと読んでた。
...2度の結婚と離婚というと恋多き女ととられそうだけど、特にそういうわけでもなく、目の前に現れた人とくっつき、それぞれの理由で離れただけと言う感じ。(1度目は相手に好きな人ができて、2度目は自分から違うと感じて)。そんな自分が2人も子供を生んだことに、「30代は繁殖期をそのまま行った」なんて自分で書いている。今の彼女は40代半ばくらいです。
日記なので、家族やよく会う友達については、あだなをつけて書いている。「自分の家族となった人は、"一般的"と言われる生活はできない部分があり、それが彼らにとってメリットにもなりデメリットにもなる」と言い、あまり気にする風もなく適当なあだ名をつけて書いているのが楽しい。
本や雑誌を書く人について、「何かの意見を言うとき、反対意見を気にしないですぐに本題に入って欲しい」というようなことが書いてあるんだけど、その通りだと思った。たとえば、「○○については、誰でも知っていることでしょうが、私はそういう方向から話しているのではなくて」というような文章はわざわざ書かなくていいと私も思う。わかる人にはわざわざ書かなくてもわかるし、わからない人にはどんな言い方をしてもわからない。反対意見を言うことが好きな人は、どんな書き方をしたって別の反対意見が出てくるものだと思うし。実際、銀色夏生は「つれづれノート」で実行していると思う(前置きなく本題に入る)。
ファンレターについて、以前はそのほとんどを楽しく読んでいたそうだが、100通に1通くらいの割合で悪意のあるものがあるそう。そういうものを読むと「もう続けて行けない」と思うくらい落ち込むそう。そして考えた末、ファンレターはもう読まない、と決めたとのこと。私は、100通中たった1通の悪意で落ち込む感受性ってとても大切だと思う。でも、その都度、著書に影響があっては、読者は安心してついていけない。感受性を持ち続けたまま、著作活動はプロであって欲しい。だから、この決断はとてもすばらしいことだと思った。
日常になにげなく感じていることを、きちんとわかる言葉で説明してくれる人。2人目の夫のイカチンと離婚する前後は「"本人から反論がある場合は、反論を書いてくれたらそれをそのまま載せる"ことにしている」と言い、実際、本人の了承を得て彼の書いたものを載せてるんだけど、イカチンの文章は何が言いたいのかわかりにくかった。銀色夏生が自身の言葉で書いた文章は、どこをとってもとてもよくわかる。物書きでないイカチンには、ちょっとかわいそうな場面でもあった。
人との関わり方も興味深い。自由業(詩人etc)で縛られずに生きているように見える人だけど、子供の学校の関係等で、嫌な付き合いがあるようで、それにどう対応してるか見るのも楽しい。
言ってることとやってることがときどき食い違ってるとこも楽しい。「人(自分)の書きかけの作品を黙って読むのは最低だ」なんて言いながら、自分も結構、人(子供)の書いたものを盗み見てたりしてる。もちろん、許される範囲でだけど。
13巻では、11歳の娘のかんちの犬、マロンに悩まされる毎日から始まり、かんちと本気でけんかしたり悩んだり、あと『死』についてよく考えたり調べたりしている年だったよう。
娘の「かんち」(今、11歳)には、相当てこずっている。かんちは、人がいやがることをしてしまったり、言われたことに素直に従わないへりくつを言う子供で、でも悪気はないように感じる。また、銀色夏生が離れていたくても、かんちは一人にされるのを嫌う。
銀色夏生は、かんちの高校卒業までの「あと7年の辛抱だ」なんて書いてるけど、そこに行きつくまでもたいへんだろうと思う。かんちの頑固さは筋金入りで、急に素直になることはなさそう。自分でうまくコントロールできないんだと思う。人ごとながら、2人にはがんばって欲しいと願う。
「死」については、「世の中の人々は必要以上に死ぬことを悲しむ」と言っている。人は誰でも死ぬのだから、そのことをまっすぐ受け止めよう、というようなこと。「死」についてあれこれ調べたり、本を読んだりしていて、それに対する考え方をわかりやすい言葉で書いてくれてるのが嬉しい。「死」という大きなテーマは自分では真剣に考えたくないものなので、こうやって真面目にわかりやすく書いてくれる人っていい。
ものごとを進めるときの手順については何かと参考になる。創作活動の部分は知らないけど、目に見えてやらなくちゃいけないことはさっさと終わらせ、カレンダーに書き込んで進めたり、子供絡みの地域の係などいつかはやらなくちゃいけないことは、早めに(この年)やってしまったり。
13巻の最後の方(2004年の2月と3月)では、幼稚園の壁に絵を描くという作業を引き受けて精力的に取り組んでいる。
彼女は冠婚葬祭に重点をおかない。年をとることを気にしない。人は常に変わるものということをいつも意識している。遊び心がある。固くない。ユーモアがある。弱くない。ものごとをさけて通らない。...読む人がいる限り、この「つれづれノート」は続けていこうと考えているそうで、今後もますます楽しみなシリーズです。
|